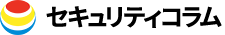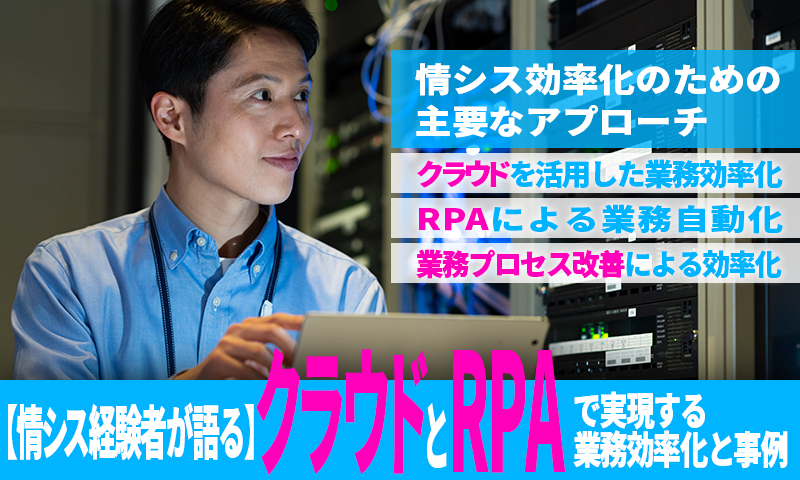情シス部門の仕事は多様で複雑です。具体的な業務を挙げていくと「運用保守、問い合わせ対応、セキュリティ対策、新規プロジェクト対応、情報資産管理、ユーザートレーニング」などと、キリがないくらいです。そして、その複雑さ故に、情シス部門では、「残業時間の増加、担当者の負担増」が発生し、「戦略的業務への対応の遅れ」などが指摘されています。また、近年は、コスト削減、人材不足、DXなどの波が押し寄せ、これらへの対応のためにも、情シス部門の業務効率化は急務となっています。
本記事では、情シス部門の業務効率化策として、クラウドサービスとRPAで実現する業務効率化を取り上げます。
情シス効率化のための主要なアプローチ – クラウド、RPA、そして業務改善
まず、情シス効率化の対応策として取り上げる「クラウドコンピューティング(以下クラウドと略します)」「RPA」「業務改善」の概要を簡単におさらいしておきましょう。
アプローチ1:クラウド活用
クラウドは、自社でサーバを持たず、インターネットを経由してソフトウェアやITインフラを利用できるサービスのことを指します。クラウドを活用することによって、情シス部門のシステム運用業務についての負荷を軽減することができます。
アプローチ2:RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
RPAは、人間が行う定常業務をコンピュータに代行させるためのソフトウェアです。情シス部門には、定常業務が多くあり、それらの業務に対してRPAを活用できます。例えば、新入社員がコンピュータを利用するために必要な「ユーザーIDの設定」をRPAに代行させることによって、情シス部門の負荷を軽減することができます。
アプローチ3:業務改善
クラウド活用もRPAも情シス部門にとってありがたいものですが、その前にやらなければいけないことがあります。それは、情シス部門の業務プロセスの見直しです。情シス部門は業務部門に対して「システム化する前に業務自体を整理しないとシステムが機能しない」という言い方をします。それは、そのまま情シス部門自身にもあてはまるのです。
次章以降では、これらの3つの対応策をもう少し詳しく解説します。
効率化アプローチ1:クラウドを活用した業務効率化
まず、クラウドの活用について、掘り下げてみましょう。
クラウド活用の基礎 – 概念とメリット
「クラウド活用による情シス部門の負荷軽減」と表現しましたが、どんな負荷がどのように軽減されるのでしょうか。それは、自社でサーバを運用するケースと対比するとよくわかります。
自社でサーバを運用することをクラウドに対して「オンプレミス」と言いますが、オンプレミスでは、自分たちで「サーバが順調に稼働しているか」「利用する機能に異常は無いか」「バックアップ処理は問題なく実行されているか」というようなチェックと異常があった場合の対応が必要ですが、クラウドを活用すると、その業務はクラウド側(サービス提供側)に任せることになります。これが、クラウド活用の基本的なメリットです。
代表的なクラウドサービスの種類
クラウドとひとくちに言ってもいくつかの種類があり、利用目的によって選択する必要がありますし、それによってメリットにも違いがあります。
IaaS(イアースまたはアイアース)は、サーバ機能のみを提供するサービスです。つまり、そのサーバ上でどんなデータベースを稼働させ、どんな業務システムを利用可能とするかは、利用する企業が決めなければいけません。ある意味では、非常にフレキシブルな利用形態だといえますが、運用負荷が軽減できるのはサーバ管理部分のみになります。
PaaS(パース)はIaaS上にデータベースやシステム開発環境などを搭載したサービスです。従って、運用負荷が軽減できる対象がIaaSよりも広がります。
SaaS(サース)はクラウド上にグループウェアや業務システムを搭載し、その機能を提供するサービスです。つまり、サーバ運用だけではなくシステム運用そのものの負荷軽減が可能になります。ただし、自社業務に合わせてシステムを変更するという柔軟性は制限されます。
業務領域別クラウド活用術
クラウド活用による情シス部門の効率化は、どのクラウド形態を選ぶかという観点と大きく関わります。いくつかの業務を抜粋して表にまとめてみました。〇印が、情シス部門での効率化が可能になるクラウドです。

*障害対応、セキュリティ対策には様々なレベルがあり、クラウドによってレベルの違いがあります。
効率化アプローチ2:RPAによる業務自動化
次に、RPAを深掘りします。RPAは情シス部門だけではなく、業務部門の効率化にも役立つものですが、ここでは情シス部門の効率化に焦点をあてます。
RPAの基礎 – 概念とメリット
RPAで業務を自動化するためには、その業務のルールを明確にし、業務のプロセスをシナリオ化して、それらをRPAに登録します。RPAは登録されたルールとシナリオに従って業務を進めてくれますので、情シス部門が抱える定常的な業務を自動化することができるというわけです。
情シス部門におけるRPA活用事例
では、RPAで自動化できる業務にはどんなものがあるでしょうか。代表的なものを挙げてみましょう。
イメージしやすい例が、先に述べたユーザーのアカウント管理です。特に新入社員が多い会社では、特定の時期に、社員番号の付与やパソコンを使うためのアカウントの登録業務が集中し、情シス部門でも一大イベントとなります。また、逆に、新入社員があまり多くない会社では、アカウント登録作業が不慣れになることがあり、ミスが発生しやすいものです。これをRPAで自動化することにより、作業負荷を減らすとともにミスを防ぐことができます。また、社員の退職によるアカウントの削除についても同様に自動化対象になります。
システムのログ監視やシステム資源の利用調査もRPAに適しています。例えば、「サーバ上のファイルやフォルダの個人別利用量を毎月調査して、ユーザーに警告を出す」というような業務はRPAの得意とするところです。
これら以外にも、「残業時間分析レポートの作成」「システム稼働状況のモニタリングとエラー時のアラートの生成」などが自動化できます。
RPA導入のステップと成功のポイント
RPAの導入プロセスとして、まず、必要なことは、要望分析です。情シス部門にある定型業務を洗い出し、どれが自動化対象になるかの候補を探します。その際に、なぜ自動化しなければならないのかも併せて考えておくと効果測定に役立ちます。「要員の業務時間削減」「業務スピードの向上」「処理ミスの抑制」などが自動化するための判断材料になりますが、「どれくらいの時間がかかっているのか」「どれくらいのミスが発生しているか」など、現状を定量的に分析しておく必要があります。
自動化対象と自動化目的が明確になれば、それらに適したRPAツールを選定することになります。
RPAの導入段階では、業務シナリオとルールの定義が必要です。「定型化、標準化されていない業務はシナリオ化できない」ことを理解する必要があります。RPAは例外処理には向きません。
実運用が始まったら、当初期待した目的が達成できているかどうかを定期的にチェックする必要があります。
クラウド型RPAとオンプレミス型RPA
RPAはその設置形態で大きく3種類に分かれます。
ひとつは、クラウド上に設置されるRPAです。これはクラウド活用のところでもお話したように運用の手間が削減できます。但し、シナリオとして他システムとの連携が必要になる場合は、クラウド内、クラウドとオンプレミス間の連携が必要になりますので、対象業務を十分に分析しなければなりません。
もうひとつは、オンプレミスとしてRPAを導入する方法です。これは、社内ネットワークで完結しますので、他システムとの連携が容易になります。
最も簡単な方法としては、デスクトップにRPAを導入する方法です。コスト的に最も安価で、かつ、短時間で設置が可能ですが、対象業務は非常に狭い範囲となります。
効率化アプローチ3:業務プロセス改善による効率化
先に「ツールよりも業務プロセス改善を優先すべき」とお話しました。目的は、あくまで業務の効率化であり、クラウドやRPAなど、ツールの導入自体を目的としてはいけません。
業務プロセス改善の基礎 – 考え方と進め方
業務プロセスを改善するステップは、「業務プロセスの洗い出し→業務プロセスの可視化→課題の発見→改善案の立案→改善案の実行→レビュー」の順に進めて行きます。
業務プロセスの洗い出しは、網羅性が求められます。というのも、見落としがちな小さな業務の中にこそ改善の余地があるからです。また、プロセスの改善という観点だけではなく「よく似た業務を複数の要員が行っている」場合もありますし、「止めてもいい業務」があるかもしれません。これらは、業務フローを作成し、それをもとに情シス部門全員で情報共有の場を持つなどすることで改善すべき業務が絞られていきます。
具体的な業務改善の手法
改善すべき業務が定まれば、改善策を検討する段階になります。
改善策として、まずはプロセスの標準化、簡素化から始めることをお勧めします。最終的にRPA、クラウド活用や、ジョブ監視ツール、サービスデスクツール等の導入、アウトソーシングという結論になるかもしれませんが、プロセスの標準化、簡素化をせずにツールに頼ってしまうと機能しなくなる可能性が残りますし、複雑なプロセスのままアウトソーシングするとコストに跳ね返ってくることになります。
業務改善を成功させるためのポイントと注意点
では、業務改善を成功に導くための注意点は何でしょうか。それは「PDCAサイクルをもとにした継続的な改善」です。業務プロセスを可視化して改善ポイントを見定め、改善策を計画するP(Plan)。それを実行するD(Do)。効果測定を行い、改善策の有効性を判断するC(Check)。改善策を見直しする必要があるかどうかを検討し改善しますA(Action)。このPDCAサイクルを継続して進める必要があります。
但し、ここに、問題があります。「戦略的な情シス部門を目指して業務効率化を行っているはずが、業務効率化という内向きの仕事になってしまう」ことです。このために、経営上層部や利用者部門に対して、目的を明確に伝えるコミュニケーションが必要になります。
ITILなどのフレームワークの活用
コミュニケーションとともに必要な要素としてフレームワークやベストプラクティスの活用があります。その中でも「ITIL®(Information Technology Infrastructure Library)」は情シス部門の業務を網羅的、体系的にまとめたガイドラインで、大いに参考になります。
ITILは、情シス部門が行う業務を34のプラクティスガイドとして提供していますので、情シス部門が行うべき業務をチェックする際に、該当するプラクティスにあてはめて考えると、改善すべきポイントも見えてきます。
クラウド、RPA、業務改善の組み合わせによる相乗効果
ここまで、クラウド、RPA、業務改善を別々に考えてきました。しかし、これらがバラバラに取り上げられるわけではなく、実際の業務の場面では、これらを組み合わせる解決策がとられることがほとんどです。
組み合わせによる効果最大化の考え方
「業務プロセスの標準化を行わないと、シナリオ、ルールとしてRPAに登録できない」とお伝えしました。つまり、RPAは標準化されたプロセスでないと機能しないという弱みがあり、業務プロセスの標準化がそれを補完することになるのです。
また、RPAの運用自体が情シス部門の業務になってしまいます。業務を効率化するはずのツールが業務を増やしてしまうのです。これを解決するのがクラウドベースのRPAです。
「業務プロセスの改善が優先」ではありますが、そこで止まってしまうと道半ばとなります。改善された業務プロセスをもとにクラウドやRPAを活用することで効果が最大化されます。
このように、今回テーマとしているクラウド、RPA、業務改善は組み合わせることにより相乗効果を得ることができるのです。
事例紹介 – 複数の効率化手法を組み合わせた成功ストーリー
組み合わせ方としては、「クラウド×RPA」「業務改善×クラウド」「業務改善×RPA」が考えられます。 それぞれの組み合わせについての成功事例を紹介します。
成功事例1:製造業A社
150名の社員を持つA社は、職人気質の製造ラインと歴史ある営業体制を中心に構成されています。
課題
ますます激化する競争を生き抜くためには、旧態依然とした業務体制にITを取り入れて、サスティナブルな組織に変わらなければいけないのですが、それを主導すべき情シス部門は、運用業務に手を取られて、身動きが取れなくなっていました。
導入した手法
まずは、情シス部門が変わらなければならないとの考えから、サーバをクラウド上に移設し、その後、情シス部門の運用業務の自動化を目指してRPAを導入しました。
導入効果
情シス部門が、運用業務に費やしていた50%以上の時間を削減することができ、その時間を戦略的なIT利用の企画、開発業務に振り分けることが可能になりました。
成功事例2:学習塾B社
7拠点の学習塾を運営するB社は専門の情シス部門を持たず、総務/経理担当者が情報システムも運用するという体制です。
課題
情報システムの専門家がいないため、サーバのトラブルや塾生管理システム、講師管理システムの利用方法に疑問があった場合、対応に時間がかかってしまい、業務の停止が頻発していました。
導入した手法
SaaSとしての塾生管理システムと講師管理システムの利用契約を結びました。ただ、どちらも、従来利用していたシステムとは機能が違っているという欠点がありましたので、思い切って「業務をSaaSに合わせる」という方針に転換しました。こうしたことで、サーバ運用やシステム運用が不要になりました。
導入効果
サーバの不具合、業務システムの操作についての疑問点は、全てSaaSのサービス会社が請け負ってくれるため、総務/経理部門はメインの業務に集中できるようになりました。
成功事例3:不動産業C社
地場の中堅として活躍する不動産業のC社は、若手社員を育成し、会社を活性化するとともに、業績のさらなる向上を目指しています。
課題
若手社員の採用増と並行して、退職者数も増えており、情シス部門はその対応のため、4月と12月がユーザーアカウント管理、タブレットの準備、共有フォルダ管理などの業務がピークとなり、他の業務にも支障が出ていました。
導入した手法
業務プロセスを分析した結果、入社/退職についての情報共有プロセスが「人事部門と情シス部門間」「情シス部門内担当者間」で標準化されておらず、場当たり的な業務になっていることが明らかになりました。業務改善策として、情報共有のルールとプロセスを整備したうえで、RPAでアカウントの付与/削除、タブレットの在庫管理、共有フォルダの割り当ての自動化を行いました。また、その際にシステムのクラウドへの移行も開始し、社内にある人事システムとの連携も実現させました。
導入効果
情シス部門の効率化として、業務量の平準化と運用に関わる時間の削減、作業品質の向上が定量的効果ですが、定性的効果としては、部門間、部門内コミュニケーションの促進も認められました。
情シス部門が効率化を推進する際の注意点と対策
業務効率化を行う際には、留意しなければいけない点がいくつかあります。
最も大事なポイントは、情シス部門自体の意識を変えることです。日々の運用業務に慣れてしまうと、改善に目を向けなくなる傾向があります。
また、ツールの導入を目的とするのではなく、達成すべき目標を定量的に設定し、それを効果判定の基準にしなければなりません。
ツール導入に際しては、やはりコスト意識が大切です。コストとベネフィットが逆転して本末転倒とならないようにしたいものです。さらには、「クラウド上にデータを配置すること」「RPAにデータアクセスの権限を与えること」のセキュリティリスクも意識する必要があります。
まとめ
情シス部門の業務効率化策として、クラウド、RPA、業務改善を取り上げました。どれもが情シス部門の負荷軽減に役立つものですが、しっかりとした業務効率化のPDCAを推進し、新たな情シス部門に変身していただきたいと考えます。