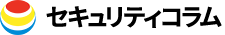デジタル・フォレンジックとは?
デジタル・フォレンジックとは、コンピュータやスマートフォン、クラウドサービスなどの機器に保存されたデータを調査・分析し、証拠として利用できる形にする技術や手法のことです。
例えば、サイバー犯罪の捜査や企業内の不正調査などで活用され、デジタル・フォレンジックが重要な場面は以下のような場合です。
企業での情報漏えい調査
例)社員が無断で機密データをUSBにコピーして持ち出していないか?
サイバー犯罪の証拠収集
例)ハッキングや不正アクセスの痕跡をログデータから特定する
法的トラブルの証拠確保
例)メールの改ざんが行われたのか調査する
デジタル・フォレンジックでは、証拠を適切に取得し、改ざんやデータ損失が起こらないよう慎重に扱うことが求められます。
証拠保全がなぜ重要なのか?
デジタル・フォレンジックにおける証拠保全とは、電子データを法的証拠として適切に扱うための手続きです。
具体的には、改ざんや破損を防ぐために、データの取得・保存・解析を厳格な手順で行うことが求められます。これにより、裁判や調査で証拠能力を維持し、正確な事実解明に貢献できます。
デジタルデータは簡単に改ざん・削除されてしまうため、適切な方法で「証拠保全」を行うことが非常に重要です。
- 従業員が不正に社内情報を持ち出した疑いがある
- 顧客データが流出した原因を特定したい
- 裁判で有効な証拠としてデータを提出したい
これらのケースで証拠保全が適切に行われていないと、下記の様な事になります。
- 証拠が改ざんされてしまい、法的に無効になる
- 必要なデータが消えてしまい、原因究明ができない
- 企業の信頼を損なう
そのため、データ取得時には「証拠保全ガイドライン」に沿った正しい手順で行うことが求められます。
「証拠保全ガイドライン」とは
証拠保全を正しく行うための参考として作成されたのが、NPO法人デジタル・フォレンジック研究会によって策定された「証拠保全ガイドライン」です。
2025年3月現在では、「証拠保全ガイドライン(第9版)」として公開されています。
日本国内におけるデジタル・フォレンジックの標準的なガイドラインは確立されていないため、このガイドラインは証拠の信頼性を確保するための重要な指針となっています。
「証拠保全ガイドライン(第9版)」では、証拠保全の基本原則として、以下の3点が特に強調されています。
- 証拠の完全性を維持する(改ざん・変更を防ぐ)
- 証拠の同一性を確保する(取得時と同じ状態であることを証明する)
- 証拠の信頼性を保つ(取得プロセスを明確に記録する)
例えば、裁判で「このデータが証拠として適切であるか?」が争点になった場合、ガイドラインに沿った証拠保全が行われていれば、証拠能力が認められやすくなります。
「証拠保全ガイドライン」は、日本におけるデジタル証拠の信頼性を高めるための参考となるガイドラインであり、法的に有効な証拠を保全するための手順が示されています。
フォレンジックは企業・法務・捜査の3分野で主に活用される
デジタル・フォレンジックは、さまざまな分野で活用されています。特に、「企業」「法務」「捜査」の3つの分野で重要な役割を果たします。
1. 企業における活用事例
情報漏えいの調査
- 退職予定の社員が、会社の機密情報を持ち出していないか?
- USBメモリやクラウド経由でデータが外部に送られていないか?
社内不正の調査
- 上司が部下のパソコンを勝手に操作していないか?
- 労働時間の改ざんが行われていないか?
例えば、退職直前の社員がUSBメモリに大量のファイルをコピーした記録があれば、それは情報漏えいの疑いが強い証拠になります。
また、PCの操作ログを調査することで、「いつ・誰が・どのファイルを開いたか」が分かります。
2. 法務(裁判・訴訟)での活用事例
証拠の改ざん・不正行為の立証
- メールの改ざんが行われていないか?
- パワハラ・セクハラの証拠(チャット・音声データ)を保全できるか?
知的財産の侵害や契約違反の証拠
- 競合企業に情報を漏らした証拠はあるか?
- 契約違反を示すデータが残っているか?
例えば、ある企業が「取引先から不当に契約を打ち切られた」として訴訟を起こした場合、メールのやり取りや契約書のデジタルデータが証拠として提出されることがあります。
改ざんや削除される前に証拠を保全することが重要であり、正しく取得したデジタル証拠は、法廷でも証拠として採用される可能性があります。
3. 捜査機関(警察・法執行機関)での活用事例
サイバー犯罪の捜査
- ハッキングや不正アクセスの経路を特定
- 犯人のパソコンやスマホから証拠を抽出
詐欺・金融犯罪の証拠収集
- オンライン詐欺の被害者と加害者のやり取りを解析
- 暗号資産(仮想通貨)を悪用した資金洗浄の追跡
例えば、ハッカーが企業のサーバに不正アクセスした場合、「どのIPアドレスから攻撃が行われたか」「いつログインしたか」をログから特定できます。
また、スマートフォンを解析することで、犯人のLINEメッセージや通話履歴を調査できます。
デジタル証拠は、犯罪捜査でも非常に重要な役割を果たし、捜査機関ではフォレンジック技術を活用して犯罪者を追跡することができます。
デジタル・フォレンジックとバックアップの違い
証拠保全とよく混同されるのが「バックアップ」ですが、これらは目的が異なります。

例えば、バックアップは「システムが壊れたときにデータを復元する」ために行うものですが、デジタル・フォレンジックでは「削除されたデータを復元し、証拠として活用する」ことが目的となります。
証拠保全の目的は、データの真正性を維持しながら調査することであり、バックアップは、システム障害時に元の状態に戻すことが目的です。
この違いを理解しておくことが重要です。
デジタル証拠の機器の種類
デジタル・フォレンジックでは、コンピュータやスマートフォン、クラウドサービスなどに残されたデータを分析し、証拠として活用します。 この証拠となるデータは「デジタル証拠」と呼ばれ、さまざまな機器に保存されています。
主なデジタル証拠の種類と保存される機器

例えば、不正アクセスが発生した場合、企業のサーバやネットワーク機器のログを調査することで、攻撃者のIPアドレスや侵入経路を特定できます。
また、スマートフォンのLINEやメール履歴を解析することで、社内の不正行為を明らかにすることも可能です。
デジタル証拠は、身近なPCやスマホだけでなく、ネットワーク機器やクラウドにも存在し、証拠は適切に保全しないと、消えたり改ざんされたりするため注意が必要です。
不適切な証拠保全とは? 証拠が無効になる原因
デジタル証拠は非常に脆弱であり、保全ミスによって証拠としての価値を失うことがあります。
以下のようなミスは、裁判や調査の場面で証拠が無効とされる可能性が高いため、特に注意が必要です。
データの改ざん・変更
- ファイルを開いたり、編集したりすると「最終更新日時」が書き換えられる
- PCやスマホの操作ログが更新され、元の状態を証明できなくなる
適切な取得方法を守らずにコピー
- 普通のコピー操作では、「いつ・どのように取得したか」の証明が難しくなる
- 適切なフォレンジックをせず、証拠能力が失われる
ログや履歴の削除
- 「証拠を隠そうとしている」と見なされる
- 不適切な操作によって、データが完全に消失する可能性がある
取得手順や証拠の管理が不十分
- 証拠保全の過程が記録されていないと、後から「改ざんの可能性」を疑われる
- 保管方法が適切でないと、裁判で「証拠の信頼性」が否定される
専門的な用語も含みますが、証拠を取得する際は、ファイルを直接開かず、ハッシュ値(MD5、SHA-256など)を記録し、証拠保全前後でハッシュ値を比較したり、データの取得は、フォレンジックツールを使用し、適切な手順を記録することが重要です。
初心者でも実践できる証拠保全
専門的な知識がなくても、基本的なルールを守ることでデジタル証拠の適切な保全は可能です。
証拠に触らず、すぐに確保する
- 不正アクセスや情報漏えいが疑われる場合、PCやスマホをそのままの状態で確保する
- 画面のスクリーンショットや写真を撮影して、状況を記録する
証拠のコピーを適切な方法で取得する
- HDDやUSBのデータは、書き込み防止機能を使って取得する。
証拠保全の記録を残す
- 「いつ・誰が・どのように証拠を取得したか」を詳細に記録する
- ログやファイルの取得日時を明確にし、証拠の信頼性を確保する
これらの基本を守ることで、有効な証拠を保全できる可能性が高まります。
専門家に依頼すべきケース
証拠保全には高度な技術や専門知識が必要な場合もあり、適切な対応ができないと証拠の価値を失うリスクがあります。
以下のようなケースでは、専門のフォレンジック調査会社や法律専門家に依頼することが推奨されます。
大規模な情報漏えいやサイバー攻撃
- 企業の機密情報が流出した場合
- サーバーが不正アクセスを受けた場合
法的な証拠としての証明が必要な場合
- 訴訟の証拠としてデジタルデータを提出する必要がある
- 不正行為(ハラスメント、契約違反など)の証拠を確実に保全したい
データの復元や削除データの解析が必要な場合
- HDDやスマホのデータが削除されたが、復元が必要
- 改ざんされた可能性のあるデータを分析したい
複雑な証拠保全が必要な場合は、専門家に依頼することで証拠の信頼性を確保できることもあります。
まとめ
デジタル証拠の保全は、適切な手順を守らないと、裁判や調査で証拠能力を失う可能性があります。
証拠を適切に保全するための重要なポイントを改めて整理します。
- デジタル証拠は、適切な方法で取得しないと証拠能力を失う
- 不適切な証拠保全(改ざん・削除・不十分な記録)は、裁判で無効になる可能性がある
- 初心者でも基本ルールを守れば、証拠保全の精度を高めることができる
- 重要なインシデントでは、専門家に依頼することで証拠の信頼性を確保できる
証拠保全ガイドラインを活用することで、法的に有効な証拠を確保し、企業や個人のリスク管理が強化できます。
適切な証拠保全の知識を身につけ、インシデントに備えることが、企業や個人を守る重要なポイントになります。
今後、よりデジタル社会が発展する中で、証拠保全の重要性はますます高まるため、基本的な知識を身につけておきましょう。
免責事項
本ページで掲載されている用語解説は、ITエンジニアや関心をお持ちの方々に情報提供を目的としており、正確かつ最新の情報を掲載するよう努めておりますが、内容の完全性や正確性を保証するものではありません。本コラム内の情報の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。

ワンビ株式会社
セキュリティエバンジェリスト 井口 俊介
高等専門学校卒業。大手企業のミッションクリティカルシステムのアカウントサポートを担当。
その後プロジェクトマネージャーにてITインフラの導入に携わる。
2020年からワンビ株式会社でエンドポイントセキュリティのプリセールスとして従事。営業技術支援、セミナー講演、コラムの執筆など幅広くセキュリティ業務に携わる。