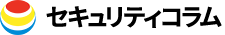近年、企業はビジネス環境の急速な変化に直面し、従来の開発手法ではスピード感が追いつかない場面が増えています。
顧客ニーズの多様化や競合環境の激化により、システムやアプリケーションのリリースサイクルを短縮することは、もはや必須条件です。
その中で注目されているのが「ノーコード」や「ローコード」と呼ばれる開発手法です。
これらはプログラミング経験がない人でも、あるいは最低限の知識しか持たない人でも、業務に必要なアプリケーションを素早く構築できる仕組みを提供します。
従来の外注型開発と異なり、社内の担当者が自ら開発に参加できるため、意思決定のスピードや柔軟性も向上します。
本記事では、ノーコードとローコードの違い、選び方、開発速度を飛躍的に高める理由、実際の成功事例、そして導入・運用のポイントまでを詳しく解説します。
情シス担当者はもちろん、社内業務改善を担う一般社員にとっても、実践的かつ現場で役立つ情報をお届けします。
ノーコード/ローコードとは?それぞれの違いと選び方
ノーコードとローコードは似た言葉として使っている方が多いですが、実際には目的や使い方に大きな違いがあります。
本章では、それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理したうえで、どのようなケースでどちらを選ぶべきかを解説します。
ノーコードの特徴とメリット・デメリット
ノーコードは、プログラミング言語を使わずにアプリケーションを作成できる開発手法です。ユーザーはGUIを用いてオブジェクトをドラッグ&ドロップし、画面や機能を組み立てます。営業管理アプリや簡単な社内申請フォームなどは、ノーコードツールを使えば短期間で構築できます。
メリットとしては、専門的なコーディングスキルが不要であるため、非エンジニアでも開発に参加できる点が挙げられます。また、テンプレートや既存のコンポーネントを活用すれば、開発期間を大幅に短縮できます。 一方で、ノーコードツールには制約が多くあり、ツールの仕様に依存するため拡張性や移行性の面で課題が生じる可能性があります。
ローコードの特徴とメリット・デメリット
ローコードは、GUIによる簡単な操作と、必要に応じたコード記述を組み合わせる開発手法です。
これにより、非エンジニアでも基本的な部分は構築でき、エンジニアが高度な機能やカスタマイズを追加できます。既存システムとのデータ連携やAPI統合、複雑なワークフローの実装など、柔軟な対応が可能です。
メリットとしては、高度な機能や複雑な業務プロセスを内製化できる点があります。システム統合やセキュリティ要件への対応も比較的容易です。
一方で、一定のプログラミング知識が必要となるため、学習コストが発生します。また、チーム内にツールの利用方法やコードの保守を担える人材が必要です。
目的別!最適なツール選びのポイント
ノーコードとローコードのどちらを選ぶべきかは、開発の目的や運用体制によって異なります。
ノーコードの場合
簡単な業務アプリや社内フォームを短期間で構築したい場合は、ノーコードが非常に有効です。
操作が直感的で、成果物をすぐに形にできるため、スピードが重視されるプロジェクトに向いています。
また、システム導入後に市民開発者として、お客様自身が保守やメンテナンスを行うことが確定している場合にも適しています。
専門的なコーディングスキルが不要なため、社内人材だけで運用・改善が可能です。
さらに、社内で利用する業務効率化ツールなど、外部との複雑なシステム連携やお客様との要件ヒアリングが不要な、独立したツール開発にも強みがあります。
ローコードの場合
ローコードは、お客様から要件をヒアリングしつつ、開発工数を抑えてシステムを構築したい場合に適しています。
特にPoC(概念実証)やモックアップの作成では、短期間でお客様に見せられる動く試作品を提供できる点が大きなメリットです。
また、ノーコードよりも高度な要件を実現しやすく、API連携や外部システムとの統合など、複雑な機能にも柔軟に対応できます。
ただし、要件をそのまま完全に実現できるかは事前検証が必要です。
要件の一部が実現できなくても許容されるケースや、開発期間とコストを最優先したい案件にも向いています。
ノーコード/ローコードが開発速度を「2倍」にする理由:内製化のメリットを徹底解説
ノーコードやローコードの最大の魅力は、従来型の開発に比べて圧倒的に速く成果物をリリースできる点にあります。
本章では、その背景にある仕組みや、企業が内製化を進めることで得られる多面的なメリットを詳しく見ていきます。
開発生産性の劇的な向上
ノーコードはコーディングを必要とせず、ローコードも大部分をGUI操作で構築できるため、開発工程の多くを短縮できます。画面設計や機能構築において、テンプレートや既成コンポーネントを活用することでゼロから作る手間を省けます。
例えば、従来3〜4週間かかっていた社内承認フローアプリの構築が、ノーコードであれば数日で完成する事例も珍しくありません。また、事前に用意されたデータベース構造やUI部品を組み合わせるだけで動作するため、テストやデバッグの時間も短縮できます。
ビジネス部門とIT部門の連携強化
従来、システム開発はIT部門や外部ベンダーが主導し、ビジネス部門は要件定義の段階で関わる程度でした。
しかし、ノーコード/ローコードなら、ビジネス部門の担当者が直接アプリ構築に参加できます。これにより、現場のニーズを即時に反映でき、仕様の齟齬や手戻りが大幅に減少します。
営業部門が自ら顧客管理アプリを作成し、その場で運用テストを行えるため、IT部門は高度な技術サポートやセキュリティ対応に集中できます。
コストとリソースの最適化
外部委託型の開発では、要件定義から納品までに高額な費用が発生します。また、納品後の仕様変更や追加開発にも追加コストが必要です。
ノーコードやローコードを導入すれば、こうした費用の多くを削減でき、社内リソースだけでシステムの開発・改善が可能になります。さらに、エンジニア不足が深刻化する中、専門人材の負担を軽減し、限られた開発リソースを戦略的な案件に集中させられます。
アジャイル開発・PoCとの相性の良さ
ノーコード/ローコードは、小規模な機能単位で素早く開発・リリースを行うアジャイル開発に適しています。
また、新規事業やサービス検証のためのPoC(概念実証)でも、短期間で試作品を作れるため、早期のフィードバック収集が可能です。
新しいサービス案を数日で形にしてテストし、ユーザーの反応を見て改善するといったプロセスが、ほぼリアルタイムで進められます。この柔軟性が、変化の激しい市場環境での競争力を高める要因になります。
成功事例から学ぶ!ノーコード/ローコードによるアプリ開発の内製化
本章では、業界や企業規模が異なる複数の事例をご紹介し、どのような課題がノーコードやローコードによって解決され、どのような成果が得られたのかを紹介します。
中小企業における業務効率化アプリ開発事例
ビジネスのスピードアップや新サービスの迅速なPoCが求められるなか、日本初のノーコード売却事例として知られる「ブラリノ」は大きく注目されています。
結婚式の招待状作成やご祝儀管理、写真共有といった機能をBubbleで開発し、短期間でサービス化したうえに売却まで実現しました。
従来の受託開発と比べ、開発コストや工数の大幅削減に繋がった事例です。
また、海外では「Support Local」というデジタルギフト購入プラットフォームがBubbleを使い、わずか3日でローンチさせ、一週間後には米国メディア「USA Today」が注目し、話題を呼びました。
このスピード感と柔軟性は、ノーコード開発の大きな強みを象徴しています。
大手企業における部門間連携システム構築事例
ローコード/ノーコードの導入によって大幅な業務効率化を達成した代表例として、住宅設備業界のリーディングカンパニーLIXILトータルサービスが挙げられます。
年間36,000件にも及ぶ申請業務を、Microsoft Power AppsとPower Automateを活用してデジタル化しました。
具体的には、これまで紙やメールでやり取りしていた経費精算や業務申請を、Power Appsで構築したフォームに一本化し、承認プロセスはPower Automateで自動化し、関係部署間の情報共有をリアルタイム化しました。
この結果、約5,000時間の業務削減、承認待ち時間の半減、誤申請による差し戻し84%減という成果を達成しています。
また、エネチェンジ株式会社では、kintoneを活用したノーコード開発により顧客管理システムを構築し、営業担当者が自らアプリをカスタマイズできるため、現場ニーズを即時反映できるようになりました。
顧客情報の重複や属人的対応が解消され、成約件数は15倍に増加しました。 このように、ローコードは複雑なワークフローやシステム連携に、ノーコードは現場主体の迅速な改善にと、それぞれの特性を活かして部門間連携を強化しています。
社内での業務効率化ツール開発による間接費削減事例
カナダを拠点とするジュエリーブランド Vitaly では、商品企画から生産、販売に至るまでのプロダクトライフサイクル管理(PLM)に多くの工数がかかっていました。
従来はメールやSlack、スプレッドシートなど複数のツールを併用し、情報が分散してしまうことで、進捗確認やデータ更新に時間がかかり、コミュニケーションロスも発生していました。
この課題を解消するため、Airtable(ノーコードデータベース) を活用し、商品開発や在庫管理の情報を一元化し、全ての関係部署がリアルタイムで最新データにアクセスできる環境を整備しました。
さらに、ステータス更新やタスク割り当てを自動化する仕組みを導入し、作業遅延や情報の行き違いを防止しています。
その結果、プロダクト開発期間は9か月から6か月へと3か月短縮し、年間で数百時間分の業務時間削減が実現することで、間接部門の人件費削減や在庫回転率の向上にもつながりました。
ノーコード/ローコード開発を成功させるための実践的ステップと注意点
ノーコードやローコードは、導入すればすぐに成果が出る魔法のツールではありません。効果を最大化するためには、事前準備や運用体制の整備が不可欠です。
本章では、導入時から運用・改善に至るまでのステップと、注意すべきポイントを解説します。
導入前の準備と計画
まず、重要なのは、解決すべき課題を明確化し、導入の目的を定義することです。
単に「便利そうだから」という理由で導入すると、ツール導入が目的化し、結果的に活用されないリスクがあります。
次に、プロジェクトチームの編成です。
IT部門と業務部門の両方からメンバーを選び、要件の洗い出しとツール選定を並行して行います。
ツール選定では、社内システムとの連携性、操作性、ライセンスコスト、将来の拡張性などを基準に比較検討します。
スモールスタートと段階的な拡大
初期導入では、全社展開を狙うのではなく、小規模かつ影響範囲の限定された業務から始めます。
例えば、部署内の申請フローや簡単なデータ管理アプリなどが適しています。
スモールスタートにより、ツールの操作感や制約を把握しやすく、早期に改善サイクルを回せます。
そこで得られた成功パターンを他部署や全社に展開していくことで、社内浸透をスムーズに進められます。
ガバナンスとセキュリティ対策
ノーコード/ローコードは業務部門が主体的に開発できる反面、シャドーIT化やセキュリティリスクの増大を招く恐れがあります。
そこで、開発ガイドラインや承認フローを設け、ツールの利用状況を定期的にモニタリングする体制を構築することが重要です。
また、アクセス権限の管理やデータ暗号化、通信の安全性確保など、セキュリティ要件を満たす仕組みを導入時から組み込む必要があります。
継続的な改善と社内教育
アプリやシステムはリリースして終わりではなく、利用状況やフィードバックをもとに継続的に改善することが重要です。
そのためには、改善サイクル(PDCAやOODA)を定期的に回す体制が必要です。
また、ツールを使いこなせる人材を増やすために、社内研修や勉強会を定期開催し、ノウハウを共有します。
これにより、開発スピードの維持と属人化防止が実現します。
まとめ
ノーコードやローコードは、プログラミング経験の有無を問わず、誰もが業務アプリやシステム開発に携われる環境を提供します。
本記事では、その定義や違い、開発速度を飛躍的に高める理由、実際の事例、導入の成功ステップまでを解説しました。
適切なツール選定と運用体制の整備、そして段階的な導入が、成功の鍵となります。
業務効率化やコスト削減だけでなく、部門間の連携強化や迅速な意思決定にもつながるため、今後さらに多くの企業で活用が進むと考えられます。
変化の激しいビジネス環境において、ノーコード/ローコードは競争力強化のための有力な選択肢となります。