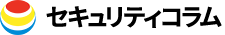執筆者:ワンビ株式会社 代表取締役 加藤 貴
2025年10月30日(木)・31日(金)の2日間にわたり開催された「旭川セキュリティシンポジウム2025」は、行政・教育機関・企業が一体となって「地方から発信するセキュリティの新たな形」を体現したイベントでした。
ワンビは、今年もブース出展および代表の加藤の講演を行い、デバイスの廃棄から始まる情報漏えいリスクをテーマに登壇した。会場は北洋ホール(北海道旭川市4条通9丁目 旭川北洋ビル 8階)。市内県外から多くの技術者、学生、行政関係者が集まり、熱気に満ちた2日間だった。

充実した基調講演 — 北海道だからこそ見えるリスクと希望
初日30日のDay1の基調講演では、大阪大学の猪俣敦夫氏が登壇。長年のサイバーセキュリティ研究の経験をもとに、「北海道の地理的・産業的特徴を踏まえた防御戦略」について語った。
特に印象的だったのは、地方では都市部のような常駐CSIRT体制を整えることが難しいため、「まずはできることから着実に積み上げる」ことの重要性を強調していた点だ。セキュリティの本質は“自衛の継続”にあると再確認させられた。
31日のDay2基調講演では、株式会社ラックの又江原恭彦氏が「IT×防災」をテーマに講演。単なるシステム防御ではなく、教育から始まる地域防災のDXを提唱した。旭川に学校を作るという具体的な構想を語る姿勢には強い情熱があり、聴講者からも大きな拍手が起こった。専門的な話に時折交じるユーモアのある脱線話も、聴衆の緊張を和らげる良いアクセントだった。
現場からのリアルな事例発表 — 北海道の強さは「現実感」にあり
このシンポジウムの魅力は、行政や大企業だけでなく、地元インフラ事業者のリアルな声が聞けることだ。
北海道電力ネットワーク株式会社は、検針メーターのIoT化に伴う苦労を赤裸々に共有。通信トラブル時の現場対応やセキュリティ検証プロセスなど、机上の理論では得られない学びがあった。
また、北海道エアポートの講演では、空港という社会インフラにおける「水際のセキュリティ対応」を紹介。社内ネットワークとWebサイトを統合し、迅速な情報共有を実現した事例は、運用現場に根差したDXの好例として印象に残った。
北海道警察の発表では、2024年に成立した「経済安全保障推進法」を踏まえ、日本の技術流出がいかに国家・企業の利益を脅かすかを警鐘。技術がテロなどの軍事転用に使われる危険性を具体的に示し、聴講者全員が真剣にメモを取る光景が見られた。
どの講演も「現実の問題に向き合う」真摯さがあり、東京の展示会とは異なる重みを感じた。
ワンビ講演「旭川発・全デバイス防衛の極意とセキュリティ謎解き」
攻撃を受けてから守るのではなく、「身内からの情報漏えい」つまり盗難・紛失・廃棄など、“終端でのリスク”にどう向き合うかを中心に話を展開した。
特に焦点を当てたのが、「データ消去の誤解」だ。
消去という言葉は一見シンプルだが、HDD、SSD、フラッシュメモリ、データセンターのストレージなど、媒体によっても場所や状況によって、方法もリスクも大きく異なる。壊せば安全という時代は終わり、SDGsの観点からも再利用と適切な消去の両立が求められている。
ここで紹介したのが、2025年10月に更新された米国標準規格「NIST SP800-88 Rev.2」である。11年ぶりの改訂で、複数回上書きの義務を撤廃し、単回の処理でもデータ無効化を明確化したほか、暗号鍵を破棄する「Cryptographic Erase(暗号化消去)」も正式に追加された。この最新動向を日本語で体系的に紹介したのは、今回が北海道初となる。

北の動物で学ぶ「消去の三守護」
講演後半では、セキュリティ学習を楽しく体験できる「謎解き」形式のワークを実施した。
北の森を守る三匹の動物たち
- シマエナガ(CLEAR:論理的消去)
- キタキツネ(PURGE:抹消)
- シロクマ(DESTROY:物理破壊)
が登場し、6つの実例に対して最適な消去方法を選ぶ問題を出題した。

55名が参加し、短時間で真剣に取り組んでくれた。結果は興味深く、正答率(全問推奨選択者)は30.9%。データ消去という基本でさえ、まだ十分に理解されていない現状が浮き彫りになった。
しかし、逆に言えばこれこそが啓発の意義であり、今後もこのようなセキュリティの啓もう活動をしていく必要があると感じた。
懇親会と地域の温もり — エゾシカと熊カレーが繋ぐ縁
なお、初日の30日の夜には懇親会が開かれ、地元ならではの料理が並んだ。中でも印象に残ったのはエゾシカのオーガニックソーセージ。スパイスとハーブが効いたジビエながら、上品で高級なローストビーフのような味わいだった。
また、「熊のカレー」は提供開始からわずか数分で完売。残念ながら味見は叶わなかったが、食べた人の感想では、臭いもなく味が深くておいしかったという感想である。用意していただいた方の地元の食文化への愛着を感じた瞬間だった。
懇親会では、講演者・参加者の垣根を越えて意見交換が活発に行われた。旭川や札幌から来たエンジニアや学生たちの真摯な姿勢、行政担当者の「市民に伝える責任」という言葉に、地域が一体となってセキュリティ文化を育てようとしていることを実感した。
東京のような慌ただしさはなく、人の温かさと誠実な好奇心が会場を包んでいた。

旭川から未来へ — 「続けること」が最大の防御
セキュリティは完成のない運用である。それは「終わりなき更新」と「日々の意識」の積み重ねだ。今回のシンポジウムでは、最新技術の話題だけでなく、「地域で守る」「教育で育てる」という本質的なテーマが多く語られた。地方だからこそ生まれる連帯感と、現実に根ざした課題意識こそが、今の日本に最も必要なサイバー防衛の姿勢だと思う。
ワンビとしても、「攻められてから守る」ではなく、「失う前に守る」という視点で、旭川をはじめとする北海道の皆さまとともに今後も情報発信を続けていきたい。そして、こうした地域密着のイベントが全国各地で連鎖し、日本全体のセキュリティ文化を底上げしていくことを願っている。
最後に
運営に携わった実行委員会の皆さま、会場スタッフの皆さま、そして温かく迎えてくださった旭川の皆さまに、心より感謝申し上げます。大変お疲れさまでした。来年もまたこの地で、共に語り合える日を楽しみにしています。