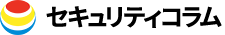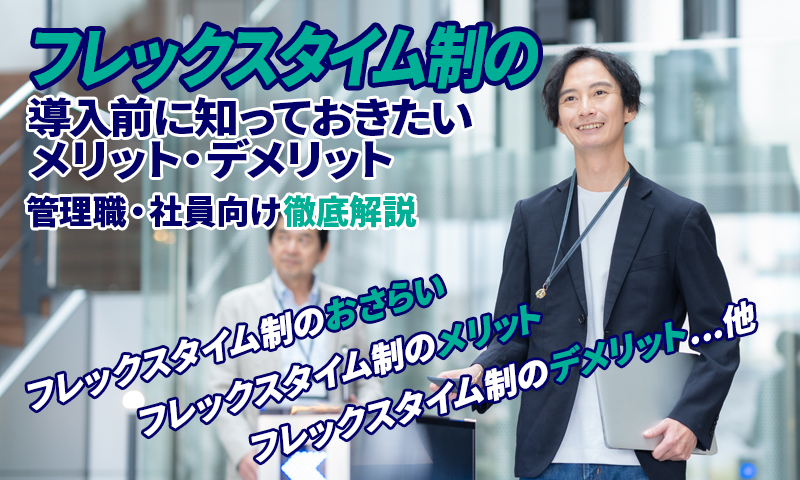フレックスタイムは通勤ラッシュの回避や子育て・介護に対応ができるなど、柔軟な働き方が実現できる制度です。フレックスタイムを導入することで、人材の確保や定着を目指す企業は少なくありません。
一方で、フレックスタイムには、自己管理の難しさや社員同士のコミュニケーションが取りづらいなどのデメリットがあります。柔軟な働き方を目指してフレックスタイムを導入した結果、業務効率が下がるのは本末転倒といえるでしょう。
本記事では、管理職・社員向けに、フレックスタイム制の導入前に知っておきたいメリット、デメリットを解説します。フレックスタイムのデメリットをあらかじめ理解しておけば、管理職・社員の双方で導入リスクへの備えができます。フレックスタイムの導入を検討している組織の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
フレックスタイム制のおさらい
フレックスタイム制(デジタル庁“e-Govポータル”労働基準法第 32 条の3)は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことができる制度です。

一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けています。 コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。
出典:東京労働局労働基準部・労働基準監督署「フレックスタイム制の適正な導入のために」
フレックスタイム制のメリット
管理職にとってフレックスタイム制は、社員の自主性を尊重しつつ組織全体の生産性向上を見込める点が大きなメリットとなります。
具体的なメリットは、まず、「生産性の向上と効率的な業務遂行」となります。社員自身のバイオリズムや集中力が最も高まる時間帯を選んで業務に取り組むことができるため、例えば、朝型の社員は、早朝の時間帯に集中力を要する業務をこなし、夜型の社員は、午後から夕方にかけて創造性を発揮するといった働き方が可能になります。
また、人材獲得と定着率の向上に大きく貢献する制度でもあります。現代では、ワークライフバランスを重視する傾向は強まっていて、柔軟な働き方を提供できる企業は、優秀な人材にとって魅力的であるため、フレックスタイム制は、人材獲得と仕事を継続しやすくする重要な要素といえます。
さらに、残業時間の削減とコスト効率の改善が期待できます。社員が業務の繁閑に応じて労働時間を調整するため、仕事が少ない日に不必要にオフィスに留まることや、上司や同僚に合わせて残業するといった慣習的な残業を減らす効果あり、時間外労働手当の抑制や人件費の効率化を実現できるでしょう。
一方、社員にとってフレックスタイム制は、仕事と私生活の調和を主体的に実現し、日々の満足度と生産性を高めるための有効な手段となります。
最も大きなメリットは、ワークライフバランスの向上ではないでしょうか。育児中の社員であれば子供の送り迎えの時間に合わせて始業・終業時刻を調整したり、介護が必要な家族がいる社員は日中のケアに時間を充てたりすることが可能になります。このように、個々の生活上の必要性や希望に応じて勤務時間を柔軟に設計できることは、生活の質(QOL)の向上に直結します。
次に、多くの都市部で働く社員にとって切実な問題である通勤ストレスの軽減が挙げられます。始業時刻を自分で決定できるため、朝の通勤ラッシュのピークを避けて出勤したり、帰宅ラッシュを避けて退勤したりすることが可能になります。満員電車内での不快感や遅延によるイライラから解放されることは、精神的な負担を大きく軽減するでしょう。
また、自己裁量による効率的な働き方と生産性向上も重要なメリットです。社員は、自身の体調や集中力が最も高まる時間帯、あるいは業務の特性に合わせて働く時間を組み立てることができます。例えば、「前日に残業で遅くなった翌日は、始業を遅らせて十分な休息を取る」、「集中したい作業がある日は早朝に出勤し、電話や会議が少ない時間帯に業務を進める」といった個人の工夫が可能になります。このように、時間に縛られず、自律的に仕事の進め方を最適化できる環境は、業務効率の向上と、より質の高い成果を生み出すことに繋がるでしょう。 このように、管理職にも、社員にもメリットがあるフレックスタイム制ですが、一方で、デメリットも存在します。次からは、デメリットについて解説していきます。
管理職が知っておくべきフレックスタイム制のデメリット
管理職は、チームや部署に対して責任ある立場のため、フレックスタイム制の導入で起きうるリスクを把握しておく必要があります。本章では、管理職が知っておくべきフレックスタイム制の具体的なデメリットを解説します。
フレックスタイム制で生じるデメリットを把握しておき、適切に対処できるように備えましょう。
チームの連携・コミュニケーションの課題
フレックスタイム制では、各メンバーの勤務時間が異なるため、情報伝達の遅れからクライアントへの対応が遅くなるリスクが生まれます。
例えば、9時にクライアントからの問い合わせがあったとしても、フレックスタイム制で担当者が11時に出社する場合には2時間も対応が遅れることになります。
本来の勤務体系であれば、8~9時にはメンバー全員が集まり情報がいきわたるため、随時クライアントへの対応が可能でした。
また、メンバー全員で集まる時間帯が減ることから、フレックスタイム制ではチームの一体感が失われるリスクも否定できません。
他にも勤務時間が異なるため、管理職の方は会議をどの時間帯に設定すればよいかなどフレックスタイム制ならではの悩みが生じます。
勤怠管理・労務管理の複雑化
働き過ぎの防止や労務負担の均一化なども管理職の仕事ですが、フレックスタイム制を導入すると勤怠管理・労務管理の難易度がさらに上がります。
フレックスタイム制では、個々人で勤務開始時間や残業が発生する時間が異なるため、所定労働時間や残業時間の把握が難しくなります。
通常の勤務体系であれば、勤怠管理・労務管理で気をつけるべきポイントは残業時間の管理でした。
しかし、フレックスタイム制になると所定労働時間もチェックするため、勤怠管理・労務管理の手間は増えます。 コアタイムを設定する場合は、各メンバーや連携のある部署との兼ね合いをみる必要があるため、悩みどころといえるでしょう。
業務の進捗状況の把握の難しさ
フレックスタイムでは、各メンバーがオフィスにいる時間が異なるため、業務の進捗状況や課題の把握が難しくなります。
例えば、通常の勤務体系で定時が18時の場合、担当者が23時まで仕事をしていたら、何かしらの課題が発生している可能性があります。フレックスタイム制の場合には、部下が、同じ時間帯にオフィスにいないことが増えるため、課題を抱えていることに気づきにくくなります。
チームや部署の課題にいち早く気づくべき管理職が、フレックスタイム制では業務の進捗状況や課題に気づきにくくなるデメリットがあります。
公平性の確保と評価の難しさ
フレックスタイムでは各メンバーの勤務時間が異なるため、業務負担に不公平さが生まれるリスクがあります。
例えば、クライアントからの問い合わせは日中にあることが一般的なため、日中に多く出社しているメンバーに負担が集中します。
反対に、クライアントからの問い合わせが少ない早朝や夕方以降に働くメンバーは、クライアントからの問い合わせを受ける負担は軽減するでしょう。
働く時間帯によって業務負担が異なるため、各メンバーに負担の差が生まれるリスクが高まります。 フレックスタイム制では、各メンバーの働くプロセスが見えにくくなるため、成果にフォーカスした評価制度にシフトする必要があります。プロセスを重視している評価制度の場合には、フレックスタイム制にシフトした場合、成果にフォーカスした評価制度への再構築が必要となります。
緊急時・トラブル発生時の対応
フレックスタイムでは各メンバーが同じ時間帯揃わないため、緊急時やトラブル発生時に人員が確保できないリスクがあります。マンパワーをかければ解決できる問題もメンバーが揃わないために、解消できないケースが生まれます。
一般社員が知っておくべきフレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制は管理職だけでなく、一般社員にもデメリットがあります。本章では一般社員が知っておくべきフレックスタイム制のデメリットを解説します。
コミュニケーション不足による孤立感
フレックスタイム制では、メンバー同士が一緒に働く時間が減るため、情報共有の機会も減ることからひとりで仕事をしている感覚に陥りやすくなります。
通常の勤務体系であれば、社員全員が同じ時間帯に仕事をしているため、情報の共有もすぐに行えましたが、フレックスタイム制では難しくなります。
気軽なコミュニケーションで息抜きもしにくくなることから、閉塞感を感じる方も出てくるでしょう。
同じ仕事に取り組んでいなくとも、気軽にコミュニケーションが取れることは働く方のメンタルヘルスに良い影響を与えます。
チームワーク・協力体制の低下
フレックスタイム制では各メンバーとの連携が取りにくくなるため、協力体制が弱まるリスクがあります。
全員が集まっている状態であれば、困っているメンバーをサポートすることも可能ですが、フレックスタイム制では連携が取りにくいため、協力し合う機会は減少するでしょう。
勤務時間が異なると、ちょっとした相談も躊躇するケースが生まれ、課員同士のつながりが希薄になるリスクもが高まります。 長期にわたり、協力体制が失われるとチーム・部署から助け合いの組織文化が失われるリスクも高まります。
自己管理能力の必要性とプレッシャー
フレックスタイム制は勤務時間の管理が個人に委ねられるため、自身で適切に管理する必要があります。
自己管理能力の高い社員は、自由な働き方でワークライフバランスを実現できる反面、自己管理能力が低いと業務が滞るリスクが高まります。 また、一般的な働き方より、フレックスタイム制は成果にコミットすることが求められるため、プレッシャーは大きくなるでしょう。フレックスタイム制は、自己管理能力とプレッシャーへの耐性が求められる働き方ともいえます。
ワークライフバランスの維持の難しさ
フレックスタイム制では、働く時間を自分で決めるため、仕事とプライベートの境目が曖昧になりやすく、結果として過重労働になるケースは少なくありません。
一日の中で何時まで働くかは自分次第となるため、仕事にのめり込んだ結果、働きすぎる方も出てくるでしょう。
従来の働き方であれば、会社が決めた定時がひとつの区切りとなり、オンとオフの区別がつけられますが、フレックスタイムは仕事の区切りも自分でつける必要があります。
評価への不安
フレックスタイム制を導入するとプロセスではなく、成果が評価の大部分を占める方向に変化します。評価軸の変化は働くプロセスを大事にしてきた方にとって、大きな不安となるでしょう。
仕事の成果は、運によって左右されるケースも少なくありません。例えば、他社とのコンペを勝ち抜けるかは、もちろん提案内容の良し悪しもありますが、提案を受ける側が決めることなので、少なからず運の要素もあります。
プロセスを評価する割合が減ると、運次第で評価がガラッと変わる可能性も否定できません。
デメリットを最小限に抑えるための対策 – 管理職・社員双方で取り組むべきこと
フレックスタイム制は素晴らしい制度である一方で、デメリットに注意しなければ、チーム・個人ともに悪い影響を受けることになります。 本章では、管理職・社員の双方がフレックスタイムのデメリットを最小限に抑えるために取り組むべき対策法を解説します。
管理職向けの対策
管理職は、フレックスタイムのデメリットであるコミュニケーションの機会が減ることへの対策を打ち出しましょう。
まずは、必ず全員が集まる時間として、コアタイムの設定をすることです。
メンバー全員が顔を合わせる時間を設定することで、報連相のしやすい時間帯を作り出します。
同時に進捗管理用のツールを導入して、進捗の見える化をすることで個々人が抱える課題に気づける環境を用意します。
一般社員向けの対策
一般社員にとっても、フレックスタイム制ではコミュニケーションの機会が減少するため、一般社員は今まで以上に情報共有を取るようにしましょう。
通話や対面でのコミュニケーションはもちろん、ツールのように誰もが見られる環境でコミュニケーションを取るようにします。
当事者以外も情報を把握しやすくすることで、確認のしやすい体制を作ることが重要です。 業務の計画もできるだけオープンにすることで、管理職や同僚が状況を理解できるようにしましょう周囲の協力が借りやすくなり、より計画的に遂行しようとする意識が高まります。
組織全体での対策
フレックスタイムは自由な働き方が実現できる一方で、適切に運用しないと会社運営に支障をきたす可能性があります。
組織全体としては、フレックスタイム制に関して以下のルール制定と周知を行い、適切に業務が行われるように管理します。
- フレックスタイム制の対象者
- コアタイムの時間帯
- 所定労働時間
- 勤務時間の記録方法
- 時間外労働・休日労働の扱い
- 運用に違反した場合の罰則
フレックスタイム制の導入にあわせて研修を行い、導入目的や注意点など対象者に再認識させるのも適切な運用を実現する方法のひとつです。
まとめ
今回は、管理職・社員向けにフレックスタイム制の導入前に知っておきたいメリットとデメリットを解説しました。
フレックスタイム制は柔軟な働き方が実現できる素晴らしい制度です。一方で、デメリットも存在します。フレックスタイム制の導入する場合には、デメリットも理解したうえで、管理職および社員の認識統一を行い、正しい運用ルールのもとで制度を導入することが非常に重要になってきます。
柔軟な働き方と適切な業務効率を実現するためにも、ぜひ本記事を参考に注意点に気を付けていただければと思います。