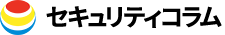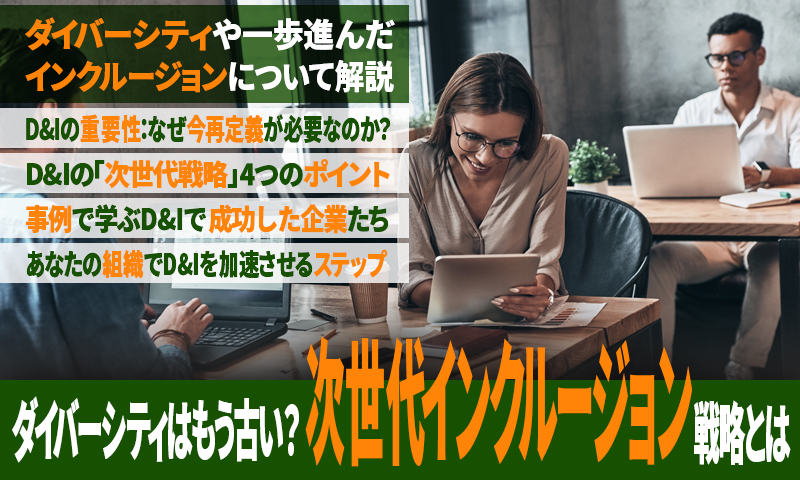多様な人材を受け入れる“ダイバーシティ”という言葉は、1990年代から登場していて、現在では一般的な用語として定着しています。
就職説明会や企業が掲げる企業理念などで、ダイバーシティのキーワードを見聞きした方も多いのではないでしょうか。
一方で、現在では、ダイバーシティに、インクルージョンが付随した“ダイバーシティ&インクルージョン”という言葉が登場しています。
人事部や管理職の方にとっては、新たに加わったインクルージョンがどのような意味となるのかは気になるポイントでしょう。
今回は、ダイバーシティ&インクルージョンを解説します。
ダイバーシティ&インクルージョンの概念を理解して、職場に取り入れることができれば、より多様な方が働ける職場が実現します。
新たに登場したダイバーシティ&インクルージョンについて知りたい方は、ぜひ、本記事を参考にしてください。
ダイバーシティ&インクルージョンの重要性:なぜ今再定義が必要なのか?
昨今では、多くの企業がダイバーシティではなく、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を目指しています。
ダイバーシティとは、性別や年齢、国籍などさまざまなバックグラウンドを持つ方が在籍する多様性のある状態・環境を指します。
対して、ダイバーシティ&インクルージョンは多様な方々を受け入れて、各々が持つ能力を発揮できる環境を目指す考え方です。
ダイバーシティ&インクルージョンを掲げている企業は、多様性を受け入れるだけでなく、多様な方々が活躍できる環境を築こうとしているため、ダイバーシティの先にあるダイバーシティ&インクルージョンを目指しています。
また、多様な方々が働きやすい環境を作れれば、人材が確保しやすくなるだけでなく、複雑化するニーズに対応できる組織にもなります。
組織としての理想論だけでなく、実務的な目線からもダイバーシティ&インクルージョンを実現する重要性は高いといえるでしょう。
検索上位記事にはない!D&Iの「次世代戦略」4つのポイント
ダイバーシティ&インクルージョンは、概念を理解するだけでなく、職場で実践・実現できるかが何よりも重要です。
多様性を受け入れるだけでなく、個々人が活躍できる環境を築くのは、言葉では簡単ですが、実現するのは容易ではありません。
本章では、ダイバーシティ&インクルージョンを実現するための4つのポイントを解説します。
心理的安全性を超える「心理的オーナーシップ」の醸成
ダイバーシティ&インクルージョンには、心理的安全性の確保が重要ですが、発言しやすい環境だけでは不十分です。
ダイバーシティ&インクルージョンの実現に必要なのは、心理的オーナーシップです。
心理的オーナーシップとは、チームの課題を自分ごととして捉え、主体的にコミットメントする姿勢です。
どのような方でも、主体的に行動できる意欲・姿勢が発揮しやすい環境が整えられれば、多様なバックグラウンドを持つ方が活躍しやすい環境になるでしょう。
心理的オーナーシップを醸成する方法としては、以下のワークショップや取り組みが有効です。
- チームやメンバーの存在意義を言語化・共有するワークショップ
- 業務における権限を委譲して自ら行動することを促す
無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を可視化するAI活用事例
ダイバーシティ&インクルージョン環境は、無意識レベルの偏見を排除しない限り、評価やコミュニケーションに影響を与えるため、実現は簡単ではありません。
一方で、人は誰しも大なり小なり、無意識レベルでの偏見を抱えており、文字どおりに本人の自覚がないため、排除するのは不可能といえます。
誰もが無意識レベルの偏見を抱えたまま、ダイバーシティ&インクルージョン環境を実現するには、AIの積極的な活用がおすすめです。
昨今のAIを取り入れたシステムを利用すれば、以下のように多様性を認めない表現や偏った属性しか活躍できない場面の検知が可能です。
- 人事評価のコメントに対して、性別や年齢、国籍に偏った表現を検出する
- 会議で発言する人の比率に対して、発言の少ないメンバーの属性を分析する
誰もが抱える無意識レベルの偏見をデータの可視化によって把握・認識することで、どのような方でも働きやすい公平な環境づくりを実現します。
企業の存在意義(パーパス)とD&Iの統合
ダイバーシティ&インクルージョンをCSR活動の一環として扱う企業は少なくありません。
一方で、企業の存在意義と結び付けて、ダイバーシティ&インクルージョンを実現している企業もあります。
企業の存在意義(パーパス)を起点とし、その目的を組織全体で共有しながら、すべての企業活動や意思決定を行う考え方であるパーパスドリブンな組織は、自社の存在意義という根本的な問いを意識しているため、従業員や求職者に強い共感を呼ぶ組織となります。
よりグローバルな目線やマイノリティな方々に共感してもらえる存在意義を掲げれば、多様なバックグラウンドを持つ方々が共感できる組織になります。
多様なバックグラウンドを持つ方々が個性や価値観を尊重してもらえると感じられれば、自然とエンゲージメントは高まり、イノベーションにつながるでしょう。
従業員エクスペリエンス(EX)を高めるインクルーシブな働き方
ダイバーシティ&インクルージョンを実現するには、働きやすい環境の整備だけでなく、従業員エクスペリエンスを高める施策が必要です。
従業員エクスペリエンスとは、職務を通じて得られる感情や経験を指しており、従業員エクスペリエンスの高い職場は働きがいのある職場と言い換えることができます。
従業員エクスペリエンスを高めるには、個人のライフステージや価値観に合わせたキャリアパスの提示や公正な評価制度が求められます。
以下の内容が従業員エクスペリエンスを高める取り組み・仕組みです。
- 育児や介護などのライフイベントとの両立を考慮した制度
- 各個人の希望や価値観に合わせたキャリアアップを支援する研修
- キャリアの希望を反映するための定期的な1on1面談
【事例で学ぶ】次世代インクルージョン戦略で導入した企業たち
ダイバーシティ&インクルージョンを取り入れた職場を目指すうえで、どのような施策を推進すればよいのか悩む方は少なくありません。
本章では、次世代インクルージョン戦略を導入した企業を紹介します。 実際に導入済みの企業からヒントを得ることで、失敗の少ないアプローチを目指しましょ
株式会社NTTデータ
大手IT企業のNTTデータでは、グローバル競争を勝ち抜くための経営戦略としてダイバーシティ&インクルージョンが必要と捉えています。
同社は単なる目標として掲げているだけでなく、2021年に「DEI推進室」を設置して、積極的な推進活動をしています。
以下の施策を全社的に実行することで、同社は多様な人材が活躍できるフィールドづくりをしています。
- 女性管理職の育成やキャリアアップの支援制度、女性のキャリア相談会の開催
- 障がい者が活躍しやすい職場環境づくりや交流会の開催
- 性的マイノリティの方が働きやすい職場環境づくりと理解を深める活動
- フレックスタイム制や在宅勤務制度など働きやすい環境の整備
株式会社LIXIL
建材製品の開発を手掛ける大手企業の株式会社LIXILでは、複雑化したニーズへの対応策として多様な従業員の潜在能力を引き出すことが必要と考えており、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。
同社では、ジェンダーによるキャリア不均衡の解消に力を入れていて、2030年3月期までには、取締役及び執行役の50%を女性にするとしています。
以下の施策を全社的に実行することで、同社は多様な人材が活躍できるフィールドづくりを行っています。
- 「心理的安全性の確保」をテーマにケーススタディの実施
- 障がい者が活躍しやすい職場環境づくりやキャリアサポート
- 性的マイノリティの方が働きやすい職場環境づくりと社内の理解を深めるワークショップの開催
- フレックスタイム制や在宅勤務制度、タッチダウンオフィス、副業制度の導入
今すぐ始める!あなたの組織でインクルージョンを加速させるステップ
ダイバーシティ&インクルージョンの導入には、概念を提唱するだけでは不十分であり、実際にアクションを起こす必要があります。
本章では、自社組織のインクルージョンを加速させるためのプロセスを、3つのステップにわけて解説します。
ステップ1:現状の組織文化を「客観的に」把握する
具体的なアクションを起こす前に、まずは現時点で組織がダイバーシティ&インクルージョンをどの程度のレベルで実現しているのか把握することから始めます。
現在の状態を把握するには、従業員へのアンケート調査やエンゲージメントサーベイを行います。
調査は、定量的なデータを集める項目だけでなく、自由記述欄を設けて、データでは測れない従業員の声を拾うようにしましょう。
アンケートの項目は以下のような項目を設けて、5段階評価で点数をつけてもらいます。
- 職場で意見を安心して言えるか
- 平等に評価されていると感じるか
- 多様な人材が働きやすい環境か
調査結果は従業員全体に公開して、自社や自分のチームがどのような状態にあるのか認識してもらうようにしましょう。
ステップ2:トップダウンとボトムアップの両軸で戦略を策定する
ダイバーシティ&インクルージョンの実現は人事部の力だけでは難しく、経営層や現場の従業員の協力があってこそ実現します。
まず経営層には、ダイバーシティ&インクルージョンの重要性を理解してもらうと同時に、全社的に取り組んでいることを発信してもらいましょう。
全社で取り組む意思を発信することで、組織のギアを一段階上げる効果があります。
現場には、働きやすい環境・働きがいのある環境の改善策を提示してもらい、実行可能な策になるまでに落とし込みをしてもらいます。
トップの経営層とボトムの現場から戦略を策定・実施してもらうことで、一体感を持った取り組みとなります。
ステップ3:スモールスタートで成果を出す
ダイバーシティ&インクルージョンを実現する取り組みを全社的にスタートすると、大きな混乱を生むリスクがあるため、まずは一部のチームから取り組むようにしましょう。
一部のチームで試験的な運用を続けて、問題がないと判断できれば、全社的な施策として展開しましょう。
ダイバーシティ&インクルージョンの実現は短期的には難しく、長期的に取り組んで実現していく必要があります。 長期的に取り組めるように、スモールスタートで失敗のリスクを限定的にしつつ、改善を重ねて最適な形を目指しましょう。
まとめ
今回はダイバーシティ&インクルージョンを解説しました。
今回解説した内容をまとめると以下のとおりです。
- ダイバーシティではなく近年はダイバーシティ&インクルージョンの視点が必要
- ダイバーシティ&インクルージョンの実現には心理的オーナーシップの醸成や従業員EXを高める取り組みなどが求められる
- インクルージョンを実現するにはスモールスタートで成果を出すこと
ダイバーシティ&インクルージョンは、今後、企業が知っておくべき考え方ですので、本記事を参考にしてみてください。