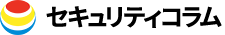新幹線が停車する米沢駅から歩いてわずか7分のところに、日本人向けに配慮された使いやすいパソコンを製造している工場があります。
こちらは、NECパーソナルコンピュータ(NECPC)とLenovoの両ブランドのコマーシャル(企業)向けパソコンを製造している工場です。NECPCのパソコンは、米沢工場で培った確かな組立品質と徹底した検査、用途に合わせた小ロットBTO対応により、すぐに現場の生産性へ直結。堅実な設計と安定供給、国内拠点ならではの迅速なサポートで日々の業務を静かに、確実に支え、長く安心して使える“企業向けのパソコン”を生産し続けています。今回の見学では、パソコンが出荷されるまでの工程をご紹介していただけました。
何を作っているのか
NECパーソナルコンピュータ(NECPC)とLenovoの両ブランドのコマーシャル(企業)向けパソコン、サーバーを同一拠点で製造しています。お届けするお客様によって用途や構成が細かく違うため、混流前提の設計が求められます。現場は「まとめて作る」よりも「要件に合わせて確実に流す」ことを優先している印象でした。
かんばん方式で作成されたパーツ便の時刻表
運用の核はトヨタのかんばん方式。必要数・必要時刻・必要場所をそろえるため、外部工場で製造されたパーツがバスの時刻表のように時間ごとに到着します。早着・遅延の双方がラインを乱すため、受け渡し点でのバッファやルートの見直しが常に検討されているとのこと。過度な在庫を置かず、仕掛品を短く保つための選択です。
人とロボットの分担
人が担うのはピッキングと組み立て。型番違い・微差調整など、人の判断が効く場所に集中させています。一方、運搬と段ボール組み立てはロボット化。重量・反復・定型の領域を機械へ渡すことで、人的工数を組み立てに寄せる設計です。無理にすべて自動化せず、ラインの変動に強いところだけを堅く固める、そんな割り切りが見えます。
工場内の動脈:自社製「トロッコ列車(勝手に命名)」
内部物流は、自社製作のパイプを組み合わせた台車を連結したトロッコ列車が循環。専用レールの大型投資ではなく、モジュールを増減できる構成を選択。工程変更や便数の調整に対応しやすく、レイアウトの“試行錯誤”がしやすいのが利点です。スピードで押すより、変更容易性を確保しているのがポイントでしょう。
小ロットBTO:数台でもカスタムに対応
この工場の特徴は、数台規模でも顧客仕様のカスタムモデルを受注生産できること。一般的に他社では、一度組んだものを開梱して再セットする手戻りが起きがちですが、米沢では最初から仕様を織り込んで流します。結果として、検査・出荷の後戻りが少なく、全体のリードタイムも読みやすくなる。BTO領域では現実的な差別化です。
技能を仕組みに載せる:マイスター制度
現場スキルの維持・継承にはマイスター制度を運用。優秀な製造員を表彰し、治具・作業標準・教育に知見を還元します。個人の上手さを皆の再現性に変える、という当たり前のようで難しい課題に、制度で向き合っている形です。
長い一本の流れ:30mライン
現在、約30mの長尺ラインをテスト稼働中。工程間の受け渡しを減らし、タクトの乱れを抑える狙いです。現時点では効果が出ているとの説明で、年末までに同様のラインをもう1系統増やす計画。一本化は効率的な反面、停止時の影響範囲が広くなるため、予兆検知や切替手順など運用側の備えが要点になりそうです。要するに、速くするだけでなく、止まった時にどうするかまでが設計範囲と感じました。
見学受け入れと地域との接点
2025年の9月は週3日の工場見学を実施するほどフル回転でした。地元の小学生からの申込みが多く、現場のスタッフは「将来、コンピュータに興味を持って仲間になってくれたらうれしい」とコメント。採用広報や情報処理教育への波及まで即時効果を求める話ではありませんが、分解・組立の現場を見た経験は、将来の進路選択に静かに効いてくるタイプの施策です。(余談ですが、見学者の質問は意外と具体的で、時に大人より鋭いです。)
見学の案内体制
今回の案内は、NECパーソナルコンピュータ株式会社 生産事業部 生産技術部 滝澤 賢一 マネージャー。工程設計と設備の役割分担、変更時の影響範囲、内製物流の調整点など、現実的な観点の説明が中心でした。用語の選び方が実務寄りで、現場の判断軸をそのまま共有してもらえた印象です。
まとめ
- かんばん×時刻表型供給で在庫と滞留を抑えつつ、ラインの同期を取りにいく運用。
- 人は判断と組立、ロボットは反復と重量という線引きで、波動に耐える工数配置。
- 自社製トロッコで“投資より変更容易性”を重視した内部物流。
- 小ロットBTOを最初から仕様織り込みで製造し、後戻りの作業を抑制。
- マイスター制度で技能を評価し、向上心を上げる。
- 30mラインは効果を確認中。増設して精算と品質の効果を向上させる。
- 見学受け入れは地域連携の継続施策。将来の人材裾野づくりとして地元への投資。
全体として、華やかな“最新鋭”を前面に出すより、選択の根拠を積み重ねている工場です。スピードと安定のどちらに寄せるか、改善のために容易に改善することを重く見た未来志向型で、それが、すべての工程・物流・人材の配置に反映されていると感じました。
最後に
工場見学ついでに「米澤牛べこや 精肉店」へ。タンとカルビの焼肉+芋煮のセットをいただきました。ざっくり食レポです。塩レモンで歯切れの良さが際立つタンと、甘い脂を控えめなタレが受け止めるカルビを白飯と流し込み、焼き野菜を挟めば後半も重くならず、締めは牛だし醤油の芋煮!ほくとろの里芋に長ねぎときのこが香り、口直しのサラダと漬物でタン→カルビ→芋煮→ご飯のループが気持ちよく回る満足なセットでした。