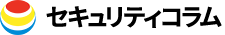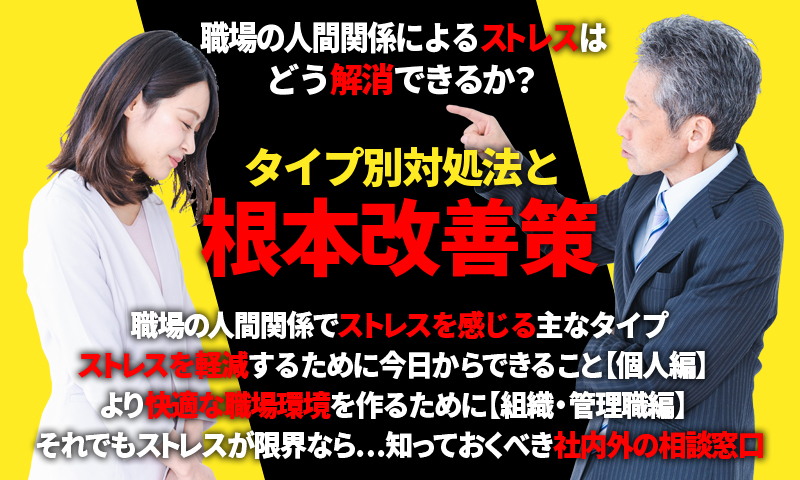職場でのストレスの原因はさまざまありますが、多くの人が人間関係をストレスの原因に挙げるでしょう。大手転職サイトの調査によると、退職理由の上位に職場での人間関係が入っていて、役職や職種に関わらず、職場でのストレスの原因になっていることがわかります。
職場での人間関係のストレスは、個人の健康を損ねるだけでなく、チーム・組織の生産性に悪影響を及ぼします。業務の多くはチームが協力することが前提で成り立っていて、人間関係に問題を抱えていると、認識の齟齬や情報の伝達不足が発生して、業務が適切に遂行できないためです。
本記事では、個人の健康維持や円滑な業務遂行のために、職場でストレスを感じる人のタイプとそれぞれのタイプに応じた対処法を解説します。職場の人間関係でストレスになる原因を理解できれば、具体的な解消方法がわかります。職場の人間関係に悩みを抱えている方は、ぜひ、本記事を参考にしてください。
職場の人間関係でストレスを感じる主なタイプ – あなたの周りにはいませんか?
人間関係の悩みで難しいところは、人に応じて対処法が異なる点です。
性格や考え方が個々で異なるため、ある人では上手くいく対処法も、別の人には応用できないケースは珍しくありません。
本章では人に応じた対処法を解説する前に、職場でストレスを生じさせる方をタイプ別に解説します。
高圧的な上司・先輩
上司や先輩の中には、威圧的な態度や感情的な言動、一方的な指示など、高圧的なコミュニケーションでストレスを与える方がいます。
具体的には、仕事のフィードバックで「何回も同じことを言わせるな!」「今すぐ答えろ」など、怒鳴り口調や責め立てるように問いかける方が高圧的なタイプに該当します。また、言葉に出さずとも、睨みつけてきたり、露骨にため息を吐いたりなど不満を態度に出す方も高圧的なタイプといえるでしょう。 高圧的な方を相手にする場合、自信の喪失や緊張を強いられるため、非常に強いストレスを感じます。
コミュニケーション不足の同僚
同僚の中には必要な情報を共有しない、報連相を怠るなど、コミュニケーションに問題のある方がいます。
コミュニケーション不足の同僚に関わると、横の連携がうまくいかないために業務が滞る、質の高いサービス提供ができないなど業務に支障をきたすため、ストレスを抱えます。
例えば、同僚が顧客への対応完了をチーム内に報告しなかったために、別のメンバーが顧客に同様の対応することで、混乱を生み出すケースがあります。
コミュニケーション不足の同僚がいることで、以下の事象が度々発生すれば、同僚の存在がストレスになることはいうまでもありません。
- 不要な作業が生まれてやるべき仕事が終わらない
- 顧客からクレームを受ける など
わがまま・自己中心的な人
会社はチームで仕事をする場所ですが、なかには自分の都合ばかりを優先する自己中心的な言動でストレスを与える方がいます。
例えば、自分が早く帰りたいばかりに質の低い資料を作成して、周囲に穴埋めをさせるタイプが自己中心的なタイプに該当します。また、チームワークが必要な仕事も、面倒・やりたくないなどの理由で周囲に負担をかける方も自己中心的なタイプに該当するといえるでしょう。 自己中心的な方を相手すると、フォローをしなければならない場面が多くなるため、大きなストレスを感じます。
陰口・噂話をする人
人は陰口や噂話が好きな生き物ですが、度を越した陰口や噂話で職場の雰囲気を悪化させてストレスを与えてくる方がいます。
例えば、噂話や陰口をよくする方の前で、少し上司に対する愚痴を言っただけで、職場中に想像もしない形で広がっていきます。「Aさんは上司のこと大嫌いみたい」「Aさんは上司のことをパワハラで訴えようとしているらしい」
噂や陰口が広まった結果、周囲の方からの見る目が変わり、職場に居づらくなるなどストレスを感じます。協力や相談もしにくくなることから、チームワークや組織の一体感が低下することになります。
責任転嫁をする人
社会人であれば、失敗の責任を認めて、反省やリカバリーに動くのが当然ですが、なかには自身の責任を認めずに責任を転嫁する方がいます。責任転嫁をする方と一緒に働くと、ありもしない失敗を押し付けられる、事後処理を担わされるなどストレスを受けます。
例えば、上司の指示で仕事をしたにもかかわらず、クライアントの要求に沿っていないと判明した場合、責任転嫁をする上司は部下の認識誤りとして報告するでしょう。
責任は上司にもあるはずなのに、ひとりで責任を負わされたり、修正対応で残業や休日出勤を強いられたりすれば、精神的に強いストレスとなります。
理不尽な要求をする人(他部署含む)
職場の中には、無理なスケジュール設定や非現実的な品質の要求など、理不尽な要求でストレスを与えてくる方がいます。
例えば、社内で強い権限を持っているのをいいことに「この仕事を明日までに終えてこい」といった無理難題を課すことがあります。
理不尽な要求をする方は、仮に要求に応えたとしても気分次第で評価しない可能性が高く、頑張って対応したとしても徒労感を感じるでしょう。理不尽な要求をする方を相手にする場合、肉体的にも精神的にも疲労することは間違いありません。
マイナス思考・批判的な人
マイナス思考や批判的な方はリスク管理や慎重な判断ができる反面、マイナス思考が強すぎると否定的な意見しか述べない、粗探しばかりするなど周囲に悪影響を及ぼします。
重箱の隅を楊枝でほじくるように批判を繰り返すため、周囲のモチベーションが下がるのはいうまでもありません。
他にもマイナス思考や批判的な方は、ラフな部署内会議の資料に対しても「フォントや文字の大きさが整っていない」などの否定的な意見を述べます。
ピントのズレた指摘を繰り返し、それに付き合っていると、精神的に疲弊します。本質的な批判をするわけでもないため、自身の成長につながらない点もストレスになるでしょう。
依存心が強い人
何かと頼ってくれる方や相談してくれる方は嬉しいですが、何でも人に頼る依存心が強いタイプは業務上の負担となるため、ストレスになります。
マニュアルで調べれば簡単にわかることや以前教えたことを何度も聞いてくるタイプは、依存心の強いタイプに該当します。
依存心の強い方を相手すると、業務時間中はつきっきりで対応することになり、自身の仕事が全く進まないこともあるでしょう。不必要な残業や作業が中断される苛立ちから、相応のストレスを受けることになります。
タイプ別対処法:ストレスを軽減するために今日からできること【個人編】
本章では紹介してきたタイプ別に、個人ができるストレス軽減策を解説します。
高圧的な上司・先輩への対処法
高圧的な上司や先輩への対処法としては、必ず冷静な対応を心がけましょう。
熱くなって対応すると威圧的な態度が一層強くなり、逆効果となります。
高圧的な方とのコミュニケーションは、客観的な事実や数字を活用することをおすすめします。例えば、「今回のプランを採用した理由は、前回のプランより早く終わることが見込めるためです。時間的に、4時間早く完了する予定です。」などです。
客観的な事実や数字に基づけば、反論がしにくくなるため、高圧的な態度を受ける可能性を下げられます。
コミュニケーション不足の同僚への対処法
コミュニケーション不足の同僚への対処法はシンプルで、その対処法は、こちらから積極的にコミュニケーションを取ることです。
チャットや通話、対面での会話など、同僚が連絡を取りやすい形で情報共有を促しましょう。
「先方への依頼の件はどうなりましたか」「見積もりの件、具体的な期日を教えてください」など認識の齟齬が起きないように徹底します。
情報共有が適切にできれば、コミュニケーション不足の同僚が原因のストレスは減少するでしょう。
わがまま・自己中心的な人への対処法
わがまま・自己中心的な人への対処法は、自身の担当範囲や役割を示して巻き込まれないようにすることです。
「見積もり作成は私の担当ではないため、代わりに担当することはできません」というように伝えて、自身の業務範囲は自分で対応するように促しましょう。
担当範囲や役割を伝える際のポイントとしては、毅然とした態度で接することです。気弱な姿勢を見せると自身の都合を強引に押し通してくるため、自身の担当範囲や役割を示して、揺るがない姿勢を見せましょう。
自身の都合を優先する人に巻き込まれる展開が減れば、わがまま・自己中心的な人に関するストレスは減少します。
陰口・噂話をする人への対処法
陰口や噂話をする人への対処法は、シンプルに距離を置くことです。
陰口や噂話をする人と関わりが多いほど陰口や噂話の対象になるため、必要最低限の業務連絡だけに留めて、距離を置けば対象になりにくくなります。また、陰口や噂話に同調すると、こちらが陰口や噂話をしていたことになるため、同調しないようにしましょう。 陰口や噂話をする人とは距離を置き、同調しないことが自身の信用を保ちつつ、ストレスを減らす要因となります。
責任転嫁をする人への対処法
責任転嫁をする人への対処法は、メールやチャット、ドキュメントなどに記録で担当範囲を明確にすることです。
ありもしない失敗を押し付けられないためにも、後から確認できるように記録を残しましょう。また、口頭でやり取りする場合、曖昧な返答をすると責任を押し付けられるため、明確な意思表示をします。
「作業見積りは行えますが、実施の方は担当できません」などのように返答して、明確に担当範囲を示しましょう。
理不尽な要求をする人への対処法
理不尽な要求をする方への対処法は、無理な要求に対応できないことを丁寧に説明することです。
例えば、無理なスケジュール設定がされた場合には、過去の実施工数を提示して実現不可能であることを理解してもらいましょう。同時に、実現可能なスケジュール案を代わりに提示して、納得してもらうようにします。
理不尽な要求に対応できないことや代替案を提示しても、納得してもらえない場合は上司や第三者に説明してもらうようにしましょう。
マイナス思考・批判的な人への対処法
マイナス思考・批判的な方への対処法は、一線を引く意識を持つことです。
マイナス思考・批判的な方の発言を真に受けると、ネガティブな方向に気持ちが引き込まれるため、話は聞いても感情まで引きずられないようにすることです。
一方で、マイナス思考や批判的な方が考えるリスク管理や慎重な判断には、理に適う部分もあるため、建設的な意見には耳を貸すとよいでしょう。
依存心が強い人への対処法
依存心が強い方への対処法は、頼りきりにならないように解決のヒントを与えて、自分で解決する習慣をつけてもらうようにしましょう。
「前回、解決した時はどうやりました?」「昨年の資料が参考になるので、調査してみてください」など解決の方向性を示すと自分の力で解決できるようになります。仮に、方向性を示しても、何度も頼ってくる場合には自分の仕事もあるため、都度対応はできないことを明確に伝えましょう。
かかりきりでは自分の仕事が終わらず、責任は果たせないことを伝えて、一定のレベルは対応するように促します。
ストレスを根本から改善!より快適な職場環境を作るために【組織・管理職編】
職場での人間関係は個人で改善できる内容もあれば、組織での取り組みが必要な内容もあります。本章では組織や管理職が快適な職場環境を作るためのポイントを解説します。
組織内コミュニケーションの活性化を促進する
個人の力に頼るだけでは、業務で必要なコミュニケーションが不足する可能性があります。
定期的なミーティングを開いて、チーム全員で会話をする機会を設けてもよいでしょう。
組織内のコミュニケーションを円滑にするには、ランチミーティングやワークショップなどカジュアルな交流機会を作るのも良い手法です。 組織内で情報共有のできるツール「Teams」「Slack」などの導入も、組織内のコミュニケーションを取りやすくする一つの手法になります。
心理的安全性の高い職場づくりを推進する
責任の押し付け合いや非難の応酬が起きる職場は、失敗を許さない組織文化が影響している可能性も少なくありません。
ネガティブな体質の改善を図るために、心理的安全性の高い職場づくりを目指しましょう。
心理的安全性の高い職場に変わるのは簡単ではありませんが、以下の施策を粘り強く続けることで、徐々に体質の改善が行えます。
- 部下やメンバーの話を最後まで傾聴する
- 上司自らが失敗例を認めて失敗を許容できる雰囲気作りを行う
- 多様な意見や異なる視点からの質問を尊重することを明言する
- 周囲に感謝する文化を定着させる
ハラスメント対策を徹底し、相談しやすい環境を整備する
高圧的な態度や理不尽な要求をする方は、自身の行為がハラスメントになると気づいていない方が一定数います。
ハラスメント防止研修を実施することで、何がハラスメント行為に当たるのかを理解してもらい、自身のおこないを振り返る機会を与えましょう。同時に、ハラスメントの相談窓口を設置して、社内に通知することで心理的安全性が高くなるようにします。
困ったときに頼れる場があると、社員の孤立感や不安感が軽減されます。
チームワークを高めるための取り組みを積極的に行う
チームワークは業務を通じて自然と高められますが、自然な醸成を待つだけでは時間がかかりすぎます。
チームの一体感を高めるためには、役割分担の重要性や合意形成の過程を体感できるチームビルディング研修を実施することもひとつの方法です。
定例会議を週次で開催して、目標の共有と協力体制を構築することでチームとして動く仕組みを作る方法もあります。
従業員の意見を傾聴し、適切なフィードバックを行う
適切なフィードバックを行うために定期的に面談をおこない、結果とプロセスを評価しましょう。結果だけでなく、プロセスを評価することで以下のメリットが得られます。
- 成果の奪い合いや失敗の押し付け合う文化を抑制できる
- どのような理由で仕事をしたのか従業員の判断基準が知れる
- 従業員の意見を傾聴する機会ができる
成果は運の要素が絡むため、ある種の波があります。プロセスの質を上げれば、より成果が上がる可能性が高まります。フィードバックを定期的にすることで、成果を生み出すプロセスの質を改善が可能です。
ストレスチェック制度を導入し、職場環境改善に活かす
社内のストレス緩和策を実施するだけでは効果が未知数となるため、定量的に判断できるストレスチェック制度を導入しましょう。
ストレスが緩和されるのが一時的な可能性もあるため、ストレスチェックは定期的に実施します。ストレスチェックからは問題点が浮き彫りになるため、改善に向けたアクションをおこないます。
例えば、上司とのコミュニケーションに問題があると判明すれば、定期的な面談を設置・回数を増やすなどのアクションを取るとよいでしょう。
従業員が気軽に相談できる社内窓口を設置し、利用を促進する
セクハラやパワハラなどのハラスメント行為を相談する先がない場合は、社内窓口を設置しましょう。
単に、窓口を設置するだけではなく、専門の相談員を配置して、外部からアドバイスを貰う体制づくりが大切です。窓口を設置すると同時に、社内には相談内容がプライバシーの観点から保護されることを通達して、利用者が安心して使えることを周知しましょう。
それでもストレスが限界なら…知っておくべき社内外の相談窓口
残念ながら日本では、職場での人間関係によるストレスは個人の問題として放置するケースは少なくありません。個人での対処が難しく、個人で抱えきれないストレスを感じた場合は、以下の相談窓口や専門機関に頼るのも一つの方法です。
- 社内のコンプライアンス・内部通報窓口
- 産業医やEAP
- 労働組合
尚、厚生労働省の窓口もありますので、紹介しておきます。
まとめ
今回は、職場でストレスを感じる人のタイプとタイプに応じた対処法を解説しました。
今回解説した内容をまとめると以下のとおりです。
- 職場でストレスの原因となる人のタイプは数多くある
- ストレスを取り除く対処法はタイプにあわせて異なる
- 快適な職場環境を作るために心理的安全性の高い職場づくりがカギとなる
人間関係のストレスは極力なくしたいものです。組織的な改善には時間がかかりますが、まずは、自分でできることから意識的にストレスに対処していきましょう。